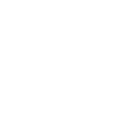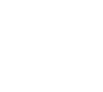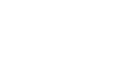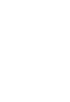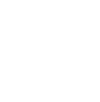2025.03.30
義歯を作る際の費用と保険適用について

東京都大田区東急池上駅前にある池上駅前城南歯科の院長、矢端恆秋です。今回は、「義歯を作る際の費用と保険適用について」についてお話をしていきます。
目次
- 義歯とは?種類と特徴
- 義歯の費用はどれくらいかかるのか?
- 健康保険が適用される義歯とは?
- 自費診療の義歯と保険診療の違い
- 義歯の費用を抑えるためのポイント
- まとめ
1. 義歯とは?種類と特徴
義歯とは、歯を失った際にその機能を補うために作られる人工の歯です。義歯にはいくつかの種類があり、患者さんの口の状態や希望に応じて選ばれます。
代表的な義歯には「部分入れ歯」と「総入れ歯」があります。部分入れ歯は、数本の歯を失った際に使用するもので、金属製のバネ(クラスプ)を残存歯に引っ掛けて装着します。一方、総入れ歯は、すべての歯を失った場合に使用する義歯で、歯ぐき全体に吸着させるように装着します。
また、近年では「インプラント義歯」や「金属床義歯」といった自費診療の義歯も人気です。これらの義歯は、保険適用の義歯と比較して快適性や審美性が高いというメリットがあります。
2. 義歯の費用はどれくらいかかるのか?
義歯の費用は、使用する材料や治療方法によって大きく異なります。
保険適用の義歯の場合、比較的安価に作ることができます。部分入れ歯は1万円~2万円程度、総入れ歯は1万5千円~3万円程度が一般的な相場です。ただし、金属を使用した部分入れ歯など、特殊な仕様のものは追加費用が発生する場合があります。
一方、自費診療の義歯は、使用する素材や精密な加工技術によって価格が大きく異なります。例えば、金属床義歯は15万円~50万円、インプラント義歯は30万円~100万円以上かかることもあります。自費診療の義歯は高価ですが、耐久性や装着感が優れており、長期的な視点で考えるとメリットが大きいと言えます。
3. 健康保険が適用される義歯とは?
日本の健康保険制度では、一定の条件を満たす義歯に対して保険が適用されます。一般的に、保険適用の義歯は「レジン(プラスチック)製」のものが基本となります。
保険診療の義歯の特徴として、費用を抑えられる点が挙げられますが、一方で耐久性や装着感に関しては、自費診療の義歯と比較すると劣ることがあります。例えば、保険の義歯は厚みがあるため、違和感を感じやすく、食べ物の温度が伝わりにくいというデメリットがあります。
また、保険適用の範囲には一定の制限があり、例えばインプラントを併用した義歯や、金属床を使用した義歯は保険適用外となるため注意が必要です。
4. 自費診療の義歯と保険診療の違い
保険診療と自費診療の義歯には、それぞれメリット・デメリットがあります。
保険診療の義歯は費用が抑えられる点が大きなメリットですが、素材の選択肢が限られ、装着感や審美性に制約があります。一方、自費診療の義歯は、患者さんの希望に応じて様々な素材や設計が選べるため、より快適な装着感や自然な見た目を得ることができます。
例えば、金属床義歯は薄く作ることができるため違和感が少なく、耐久性も高いのが特徴です。また、シリコン義歯は柔らかい素材を使用しているため、歯ぐきへの負担が少なく、痛みを感じにくいというメリットがあります。
5. 義歯の費用を抑えるためのポイント
義歯の費用を抑えるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
まず、保険診療の範囲内で作れる義歯を選ぶことで、費用を大幅に抑えることができます。保険の義歯でも、適切にメンテナンスを行えば十分に機能します。
また、義歯の耐久性を高めるために、定期的な調整やクリーニングを受けることも重要です。義歯が合わなくなった場合でも、早めに歯科医院で調整を行うことで、新しい義歯を作り直す費用を抑えることができます。
さらに、自費診療の義歯を選ぶ場合でも、クリニックによって費用が異なるため、事前に見積もりを確認し、納得した上で治療を進めることが大切です。
6. まとめ
義歯の費用は、保険適用か自費診療かによって大きく異なります。保険適用の義歯は費用を抑えられる一方で、素材や設計の制約があります。自費診療の義歯は費用がかかるものの、装着感や審美性に優れているため、快適に使用できます。
患者さんの口の状態や生活スタイルに合った義歯を選ぶことが、長期的に快適な生活を送るための鍵となります。義歯の選択に迷った場合は、歯科医師と相談しながら、自分に合った最適な治療法を見つけることが大切です。
池上駅前城南歯科では、患者さんのニーズに合わせた義歯治療を提供しております。義歯についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
歯科医師 院長 矢端 恆秋
ご相談はこちらから → https://dental-apo.jp/net/1e7c8ae6/#select